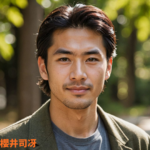GW【登校しぶり・不登校】ゴールデンウィークと5月病の対策。家と学校でできる予防策

つかさの教室、教室長のつかさです。
休み明けは仕事行きたくないと思うのと同じように、学校に行きたくないな、と感じる子どもたちも多いです。
学校の先生向けに、また不登校気味の子を持つおうちの人向けに書きます。大人でもしんどくなる5月子どもと一緒に乗り越えませんか?
5月病とは
大人でもなります。以下に医学会の説明を引用します。
入学や就職にともない学校や職場で新たな生活がスタートします。新生活は、慣れないことも多く知らず知らずのうちにストレスがたまるものです。気づかないうちに無理をしてしまうことも少なくありません。また、仕事の内容や環境が自分に合っていないために、「適応障害」を起こしていることもあります。こうして1カ月が過ぎ5月になる頃に、身体のだるさ、疲れやすさ、意欲がわかない、物事を悲観的に考えてしまう、よく眠れない、食欲がないなどの心身の症状が現れることがあります。これを「五月病」といいます。五月病は、正式な医学用語ではありませんが、一般に、この季節に学生や新入社員に起こりやすいため、こう呼ばれています。
大阪府医学会HPより
「適応障害」よく聞きます。不登校や登校しぶり、気分が落ち込む、対人トラブルなど、様々な症状が現れていきます。
このまま放置しておくと、うつ病にも発展しかねません。
しかも、「5月病」は真面目な性格の人がなりやすい傾向にあります。こうしないといけないと強く思うがゆえに、ストレスを抱えてしまう。
子どもたちのストレスは大人で軽くしてあげましょう。
GWが不登校のきっかけになる

ゴールデンウィークは生活リズムが乱れがちになります。
学校も部活動も休みならば、学校側で生活リズムをコントロールするのは難しい。おうちの人も仕事がある人はありますから、コントロールが難しい。
生活リズムの乱れから不登校まで、そんなに時間はかかりません。
生活リズムの乱れを事前に予防しておくことが大切です。
夏休みくらい長ければ、後半でリズム取り戻せますけど、ゴールデンウィークは時期も悪いのです。「新学期頑張ろう」の疲れが出てくるのがこの時期なんです。
大人が、生活リズムを管理する必要がありますよ。次の章で対応策を紹介しています。
【対応策】早めに対応しましょう
解決策は「日頃からストレスを溜めないことが大切」とよく言われます。こんなことは大人も、分かってるんです。分かってても適応障害になりますよね。
そのまま、我が子(生徒に)「ストレスためんなよ」ではダメなんです。もう一歩進んで考えてみましょう。
【予防策】と【対応策】について書きます。予防策は、兆候が現れる前から実行して欲しい事。対応策は、兆候が出てきてからの行動です。
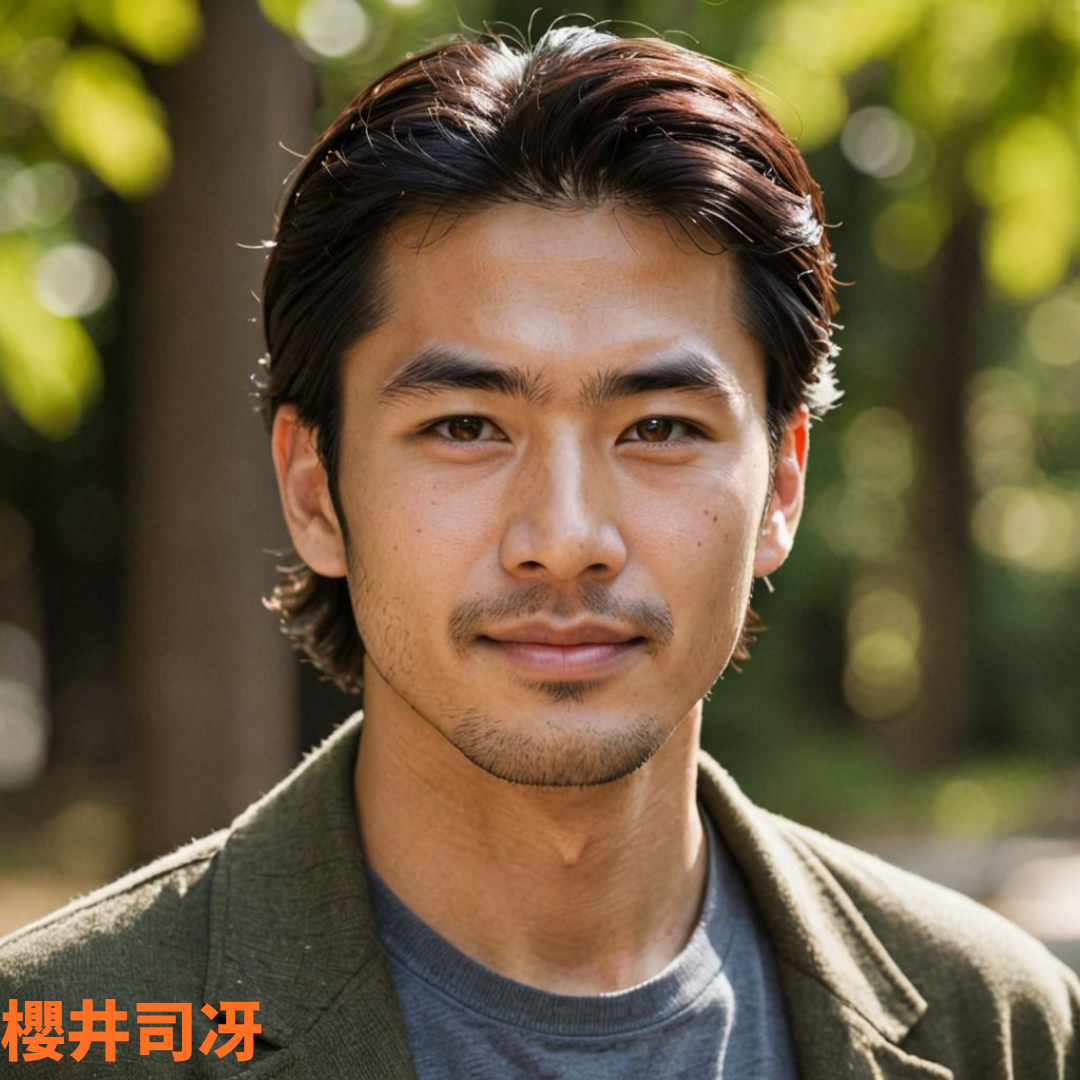
対応策の時点で遅いじゃん。ではなく、なにもしないよりマシなんです。
適応障害の放置は悪化します。反抗される方がいいです。
家庭における対策
- 【予防策1】インターネット端末の接続制限(約束する)
- 【予防策2】親子でできる共通の趣味を見つけておく
- 【予防策3】変化が大きな時期はいつも以上によく観察する。
- 【対応策】時には遊ぶことも大切
【予防策1】インターネット端末の接続制限(約束する)
「夜九時以降は使わない」というのは最近の子には酷ですかね。「明日予定無いんだから良いじゃん」となる可能性もあります。
親子でルールを決めておきます。それが確実で、お互いの意見が通ります。
・次の日が学校・部活・習い事:22時まで使える。23時には寝る。
・次の日が休み:23時半まで使える。24時には寝る。
・朝は6時から使ってもいい。端末はリビングで充電する。
定期的にスクリーンタイムを確認しましょう。ネットトラブルも未然に防げます。
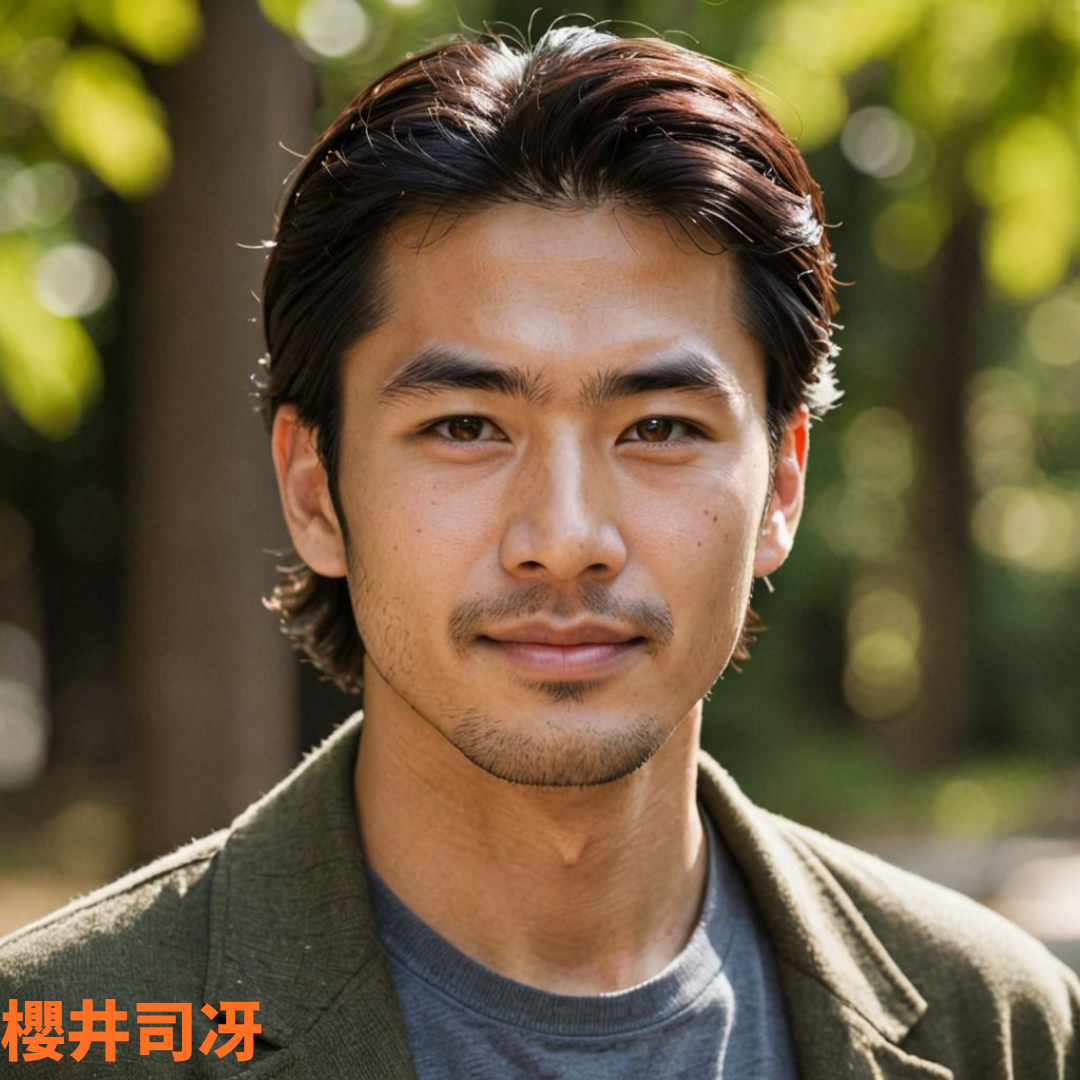
インターネットに接続できるデバイスを与えるなら、管理する必要があります。
もし、ルールが守れない場合は、解約でいいと思います。
【予防策2】親子でできる共通の趣味を見つけておく
親子でできる事であれば、時間の管理が親側で行いやすいです。生活リズムを管理しつつ、ストレスを発散させてあげましょう。
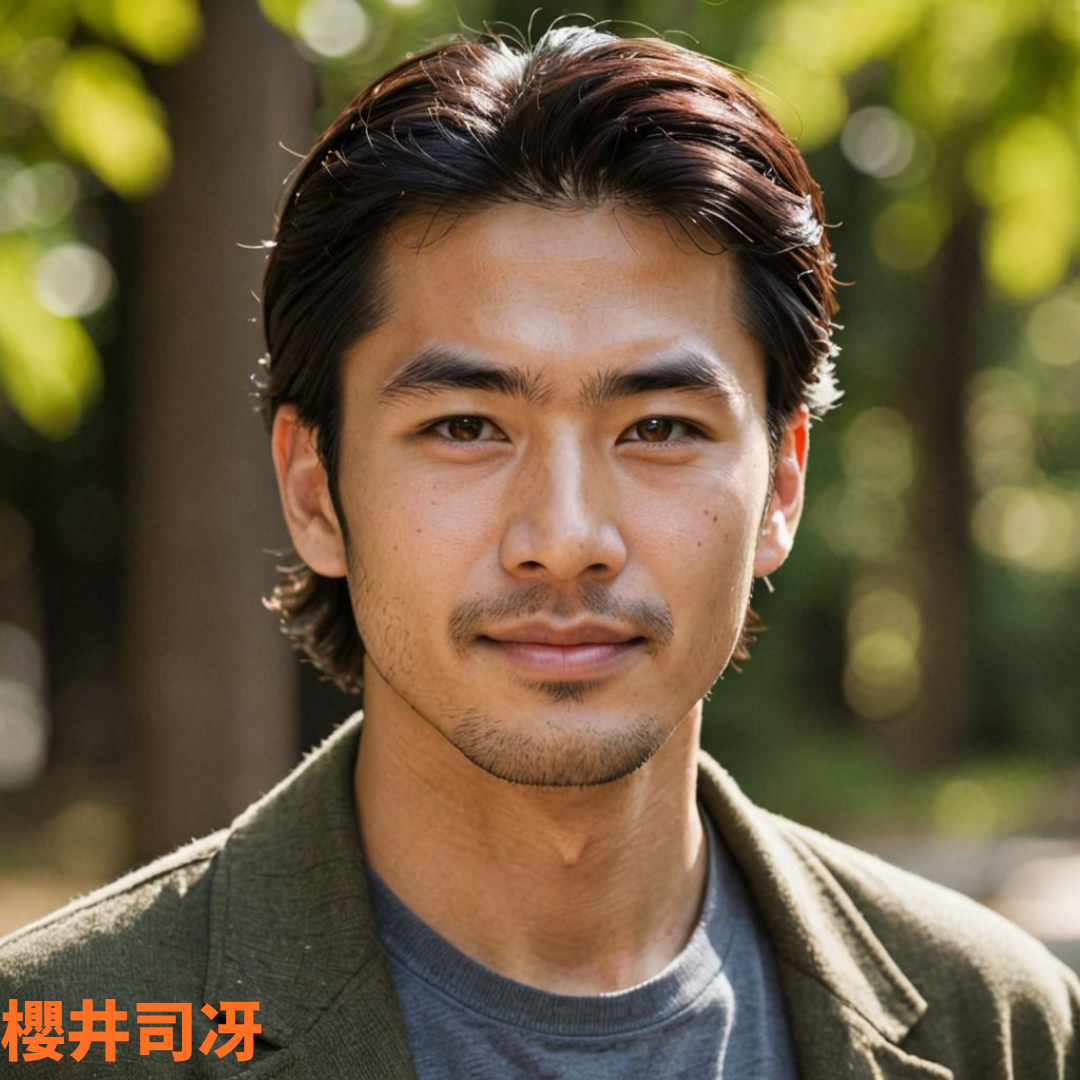
今度の日曜日映画見に行こう。来週の土曜日はつりに行こう。なんでもいいです。
ゲームでもいいです。時には、負けてあげるくらいが良いあんばいです。
【予防策3】変化が大きな時期はいつも以上によく観察する。
小学校の時は良くアマプラでアニメ見てたのに、中学校に入ってからアニメ見なくなったな。
今日は帰ってきてからいつもより元気がない気がするな。というような些細な変化を敏感にキャッチします。
常々コミュニケーションをとり、なぜそうしないのか聞いてみましょう。趣味や好きなことから離れるのは、適応障害の兆候です。
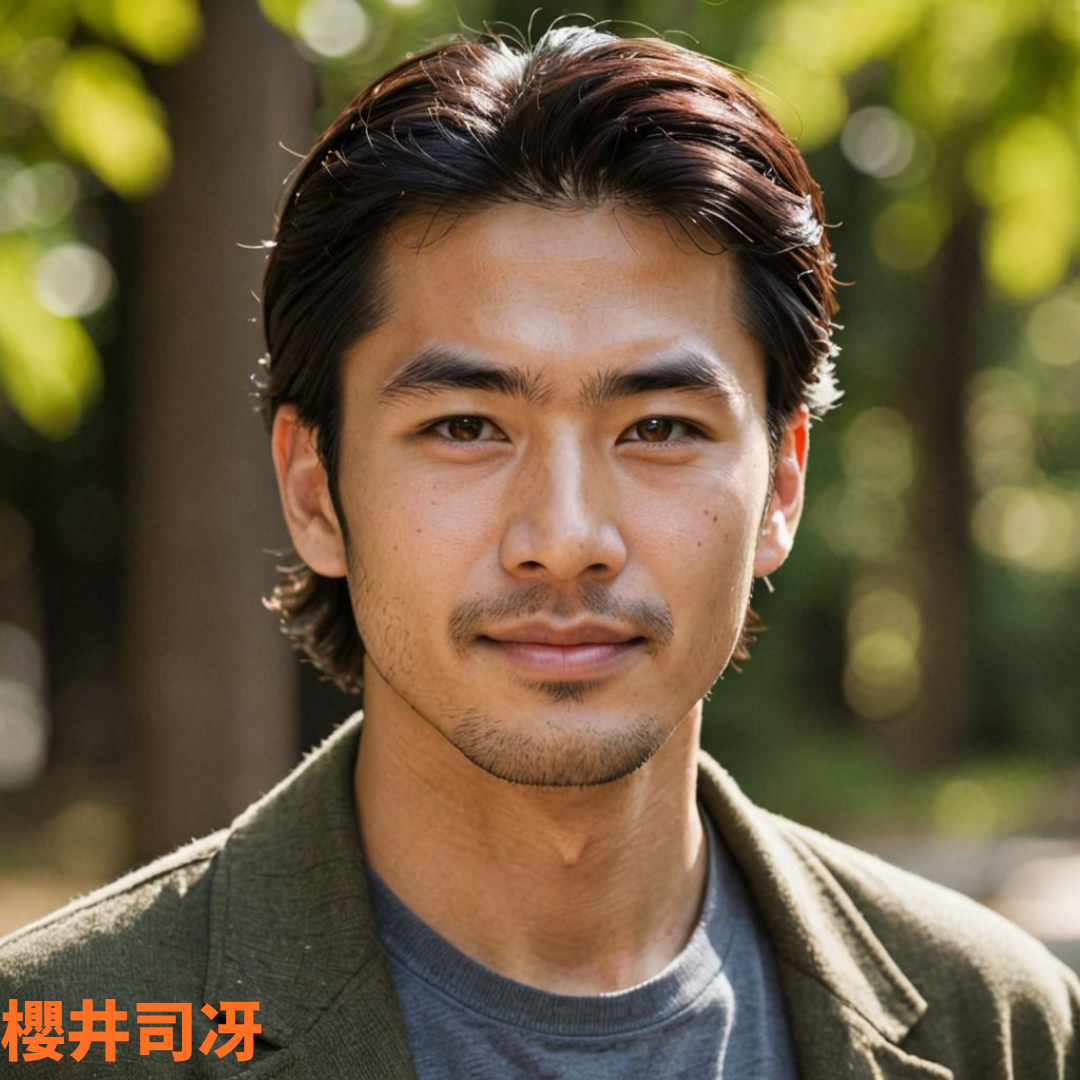
私なんかも疎い方ですが、夕飯ときは「学校の会話をする」習慣をつくっておけば、気づけなくても自分で話してくれるようになるかもしれません。
【対応策】時には遊ぶことも大切
学校、学校、学校と意識が学校ばかりに集中していると疲れます。大人で言うと仕事、仕事、仕事、しんどいですよ。
生活の中に「あそび」がないと、死んでしまいます。
逆に遊び、遊び、遊びというのは良くないですよね。大人はそのバランスを管理してあげます。
疲れている様子がある場合は、休みの日などに親子でお出かけしてみましょう。スマホやゲームなども目に疲れが出ますし、たまの外出が息抜きになります。
近くの公園でも良いんです。気晴らしに河原で昼寝しても良いんです。親子なりの外出をしてみてください。
家じゃない場所に出かけるというのもポイントです。家にいてできるストレス発散だと、「ずっと家にいれば良いじゃない」となるのです。
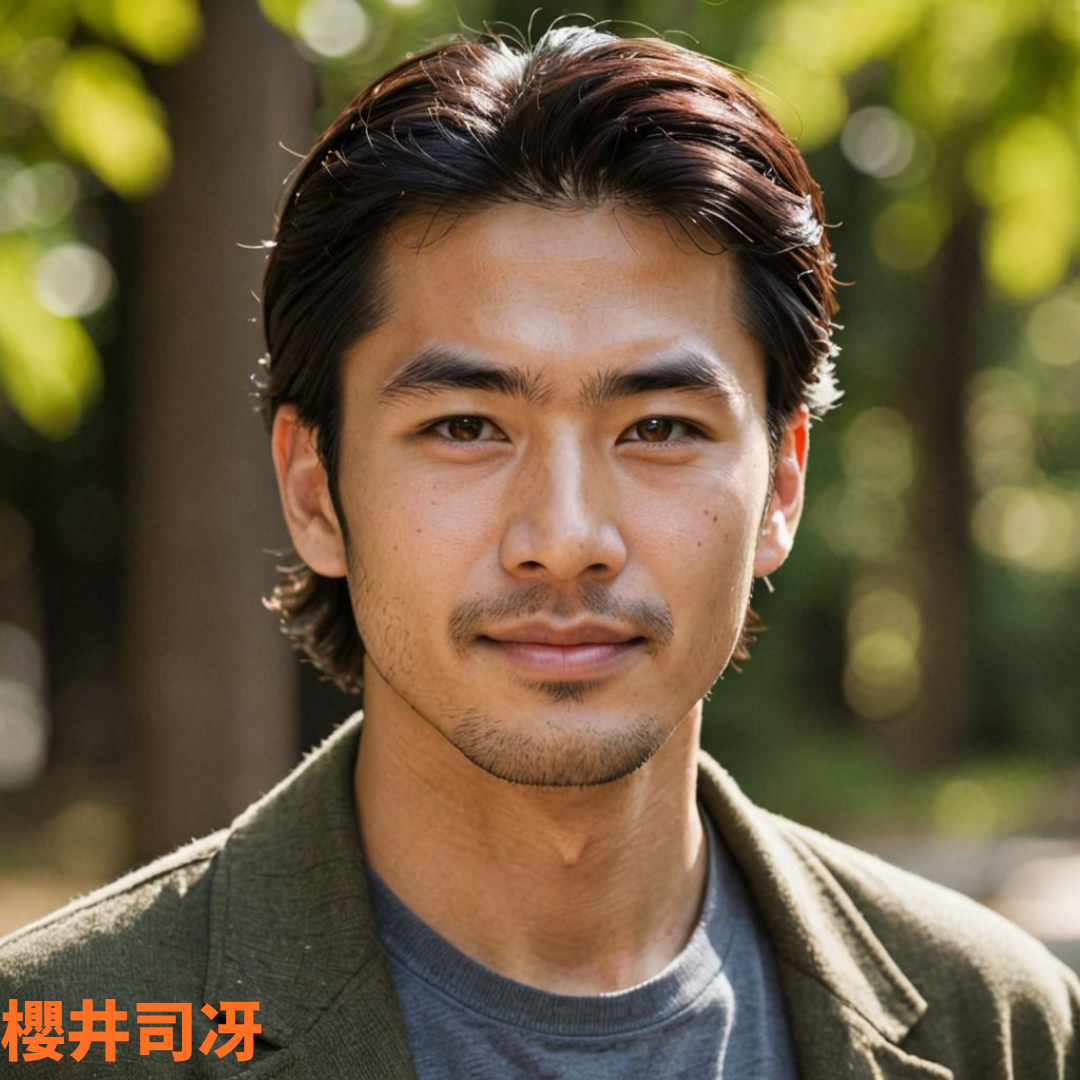
自分も気晴らしが必要ではありませんか?
息子・娘と二人でお出かけして息抜きしましょう。
保護者向けに別の記事でも不登校について解説しています。
学校における対策
当たり前ですが、不登校や登校しぶりが起こったら、対応できることが一気に減りますし、逆にしなければいけないことも増えます。予防策に心血注ぎましょう。
【予防策1】よく観察
1学期は安定するまで、教室にいる時間を長くします。孤立している子やトラブルになりそうな事象を観察しておきます。
その場で注意したり、話しかけたりします。
若い先生に言っておきたいのは、話しかけてくる生徒は基本的に大丈夫です。話しかけてこない生徒に積極的に話しかけに行きましょう。
トラブルを起こしがちな生徒や孤立しがちな生徒をチェックしておきます。
うざいくらいが先生らしいです。不登校になるよりか、嫌われる方がその子のため。
【予防策2】みんなでするイベントを用意
勉強ばっかりの学校生活は行きたくありません。ほどよい息抜きの場を先生側で用意するというのはどうでしょうか。学年で相談しても○。
GWおわったら、お楽しみ会なんてのも良いじゃないですか。学活の10分くらい使って楽しいことすれば良いんですよ。簡単なレクでも良いんです。
学校は勉強するだけの場ではないんですから。
【予防策3】GWに部活を入れる
案外良いと思うんですよね。午前中に部活あれば、生活リズム以外と整います。
外部移行進んでいますが、外部に移行したとしても、大型連休は練習し放題なので、練習の予定でいっぱいになりますよ。
【対応策1】保護者連携+友達パワー
登校渋りは早めに対応すれば、解決することもあります。おうちの人と連携して、朝の登校前等に友達と家に行く計画を立てます。
友達と一緒なら学校行こうかな、となる可能性もあります。わざわざ来てくれてありがとうという気持ちで一緒に登校する可能性もあります。
ただ、友達パワーには注意が必要で、タイミングが大切です。友達パワーを使いすぎると、友達が来るときしか学校に行かないというフェーズに移行します。タイミングはおうちの人や管理職、学年主任などと相談しましょう。
可能なら4月病も防ぎます
小学校を卒業し、中学校に入学する4月。小学校までの授業とほとんど変わらないのに、なぜか、「学校に行きたくなくなる」そんなこともあります。
小中ギャップと呼ばれています。学校側では小中連携をしっかり行うしかありません。兆候がある生徒は徹底マークです。
おうちの方も4月は、十分に観察してあげましょう。特に卒業式が終わったら春休みなので、新入生になる中1、高1になるときは最新の注意をはらいましょう。
今後は、スマホなどの管理が必要
予防策にも書きましたが、スマホの管理が必要です。
一人だけの問題ではなく、LINEなどはグループの通知が睡眠の妨げになったりします。
学校側も○○時移行は使わない、などと指導しますが、保護者同士で子どもたちの環境を整えてあげます。
時には友達の子の親に連絡しても良いと思います。その友達のためにもなります。我が家のスマホルールはこのようになっています、と説明しておくのも良いと思います。
小学生の場合は学級懇談会などで「使用時間」共通理解しておけば良いとも思います。
保護者向けに別の記事でも解説しています。