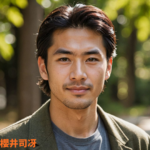【先生向け】不登校の生徒と関わるときに注意したこと。凡事徹底で改善する!
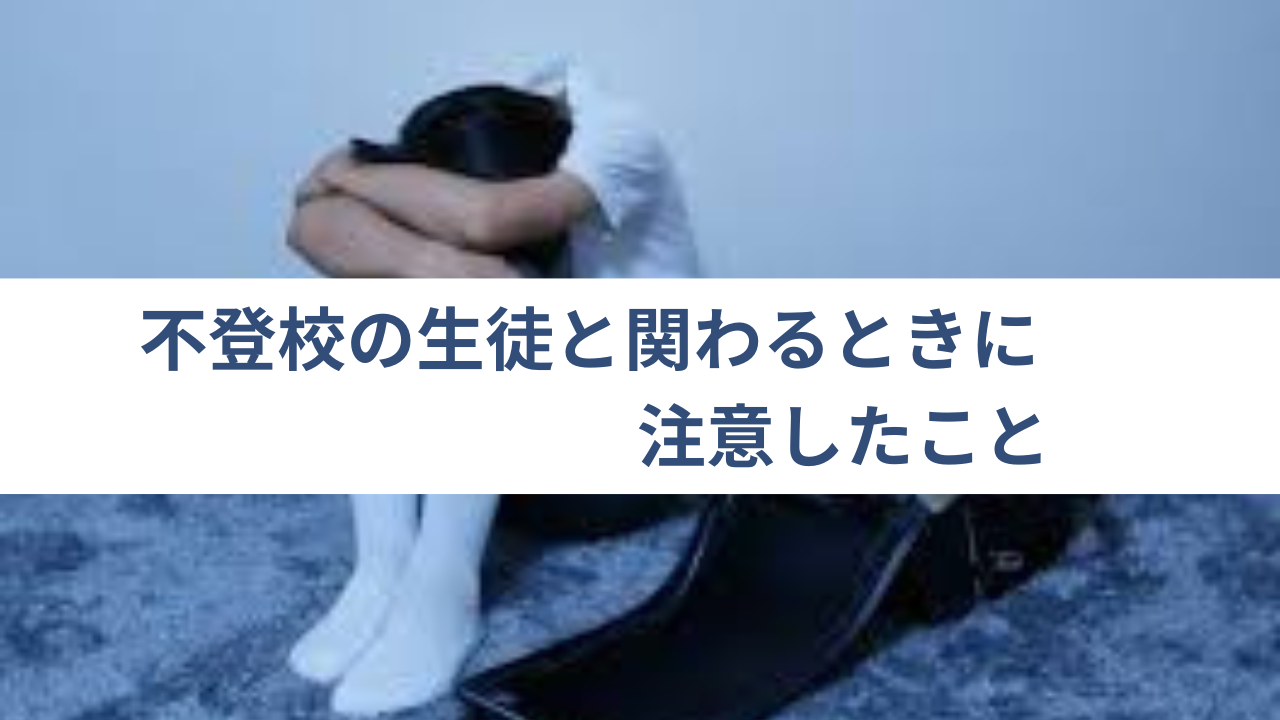
不登校傾向のある生徒も含めると年間で33万人いると言われています。どんどん増えていくと思います。
私が不登校生徒と関わる中で大切にしたことを綴っていきたいと思います。私の中でのキーワードは「凡事徹底」です。
不登校・不登校傾向との関わり
結構身近という認識を
不登校傾向のある生徒が33万人いる。(2019年時点)
令和5年度の文部科学省の統計で、小学校18,980校、中学校が9,944校、義務教育学校(小中学校)207校、高等学校4,791校、特別支援学校1,178校、中等教育学校が57校となっている。
全国に小学校~高校生までの学校が約35,000校あるということ。
小学校は6年間とか、義務教育学校は9年間とかはひとまず置いておいて、1校あたり10人くらいはいそうということ。
33万人居るから多いな。という漠然としたものではなく、1つ学校あたり10人居ると具体的に考えたら意外と多いのではないですか?
先生としての心の持ちよう
「日常の業務が忙しい」でも、不登校の生徒には関わっていかないといけない。
どうせ関わっていくなら、不登校傾向のある生徒は、登校してくれる方が負担減になると思いませんか?
すでに不登校になっている児童生徒に関しては、慎重な対応が求められる部分も多いですが、やはり自分が担任している1年で改善に向かわせられると最高ですよね。
改善というのは学校に来る方向に向かうだけではありません。
フリースクールに行く、自分で勉強を始める、なんでもいいんです。
その子にとって良い方向に進めるように、力を尽くしましょう。
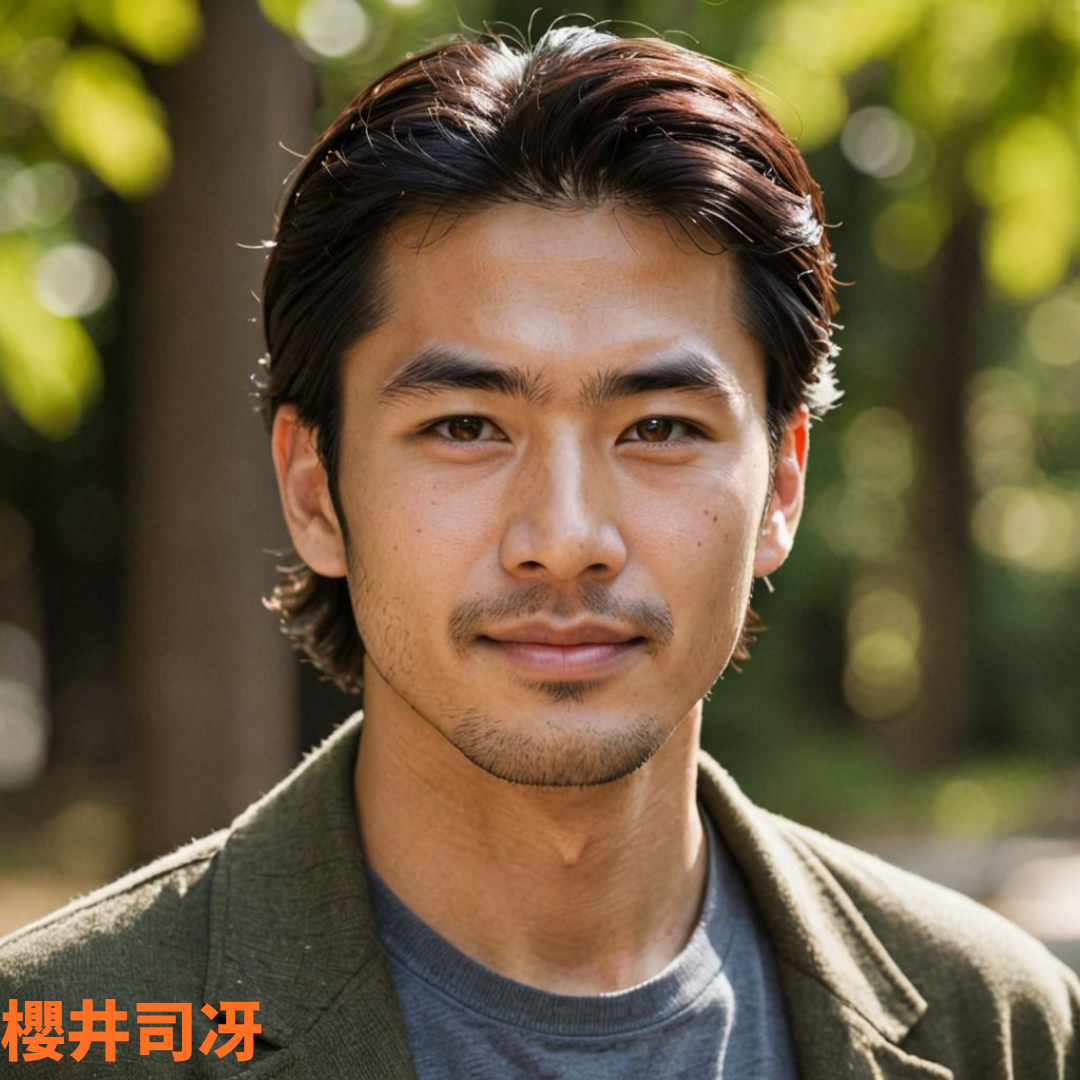
自分の受け持っている生徒が不登校になってしまっても落ち込む必要はありません。
原因があれば、原因を取り払ってあげ、不登校が改善するように働きかければ良いのです。
凡事徹底とは
凡事徹底とは「誰にでもできる当たり前のことを誰にも真似できないくらい徹底してやる」ことです。
不登校児童・生徒の対応についても同じことが言えます。
誰にでも不登校対応はできますが、不登校なんてほっとけば良いと諦め半分な先生も元同僚にはいました。
そこを徹底して行います。他の先生にはない、自分だけの魅力になります。
不登校児童・生徒への凡事徹底

不登校児童生徒の状況は一人一人異なります。10人いて全員に同じことをして、不登校が改善するのは期待薄です。
全員に共通してやるべきこともあります。
- 生徒理解
- 連絡はまめに(保護者にも本人にも)
- 本人に会う(生徒によってはNG)
- 言ってはいけない言葉は絶対言わない
やるべきことをしてから、個にあった支援に入ります。
凡事徹底1:生徒理解
まずは、生徒理解です。どんなことよりもまず、生徒理解です。
担任、生徒指導担当、生徒支援担当、学年主任部活動顧問どの役職であったとしても、生徒理解から入りましょう。
前の学年、前の学校からの引き継ぎがあれば目を通して、どんな対応がNGなのか確認しておきましょう。
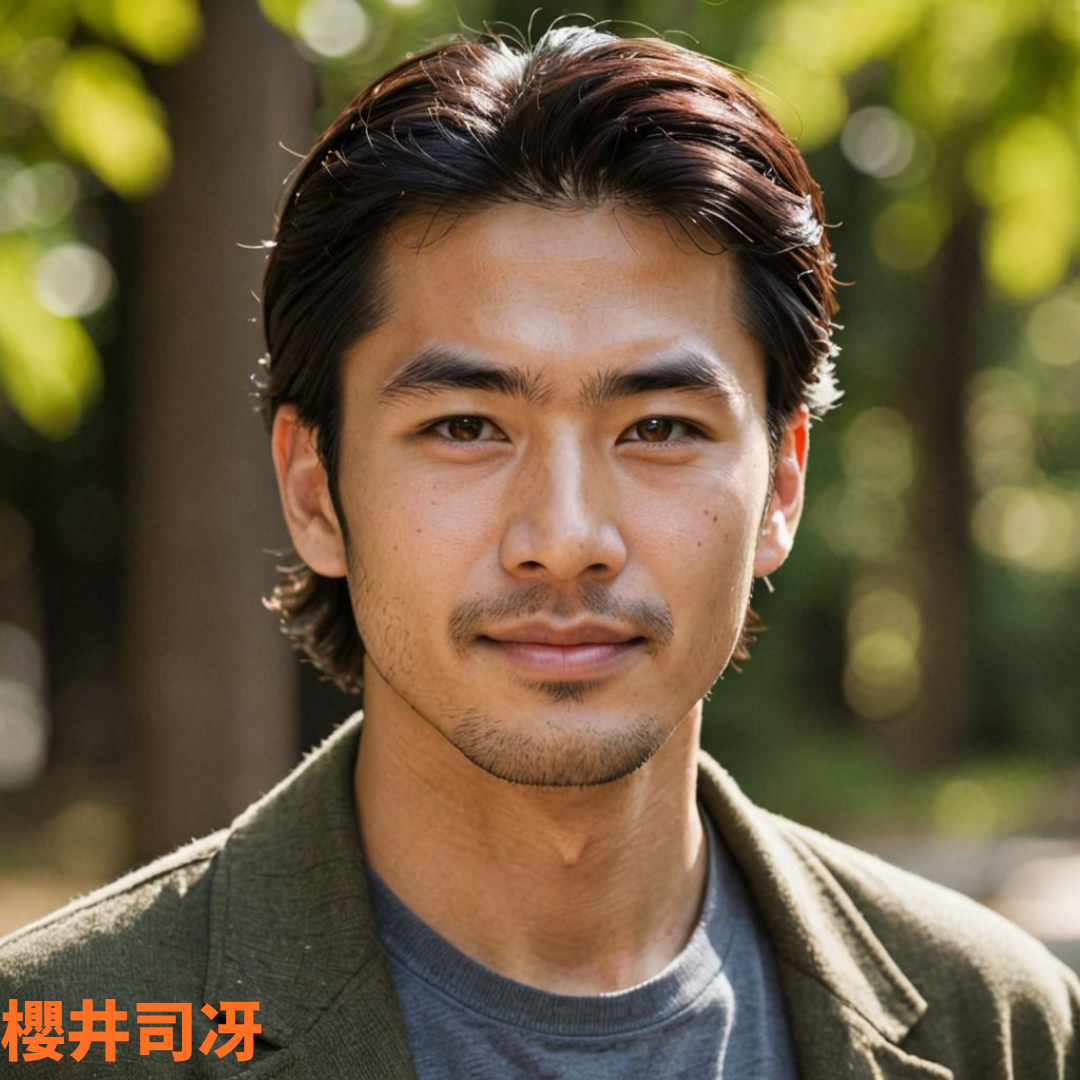
特に新入生に不登校・不登校傾向のある生徒がいる場合は入学式よりも前に把握しておきましょう。
不登校となった原因がはっきりしている場合、改善にも向かいやすいのでよく理解しておきましょう。
友人関係の問題・起立性調節障害などによる体調不良・クラスがあれているから行きたくない・担任が合わない、色々な理由を言う生徒がいましたが、本人たちも真剣に悩んでいる場合が多いです。
場合によっては不登校生徒の友人などに聞いてもいいと思います。
凡事徹底2:連絡をこまめに(週2回 継続する)
欠席連絡は、毎朝という学校も多いと思いますが、不登校生徒の場合特例となっていることが多いのではないでしょうか?
不登校児童生徒の保護者の方から相談もあると思いますが、毎日の連絡が負担で、保護者の方の精神的負担が大きくなることもあります。
その子の休みの日数や不登校の期間にもよりますが、長く休むことがわかっている子の場合は週に2回程度の連絡がちょうどいいと感じるご家庭が多いです。
完全に来ていない場合、最近どのような事をして過ごしているのか・体調はどうか・勉強に気持ちは向いているかなどを確認する程度になりますが、こまめに連絡をとり、学校へ行くきっかけになりそうなことがないか気にしておきましょう。
途中で連絡頻度を下げてしまうと、学校に来る機会を失いかねません。
継続は力なり、情報収集も兼ねているので変化に敏感になりましょう。
凡事徹底3:本人に会う(生徒によってはNG)
私は、少ない生徒で、月に1回程度家庭訪問をおこないました。
もちろん、もっと家庭訪問していた生徒もいます。
先生に会いたくないという、生徒もいると思いますが、基本的にはどんな先生が担任なのか、会いたいなと思っている生徒がいると思っています。
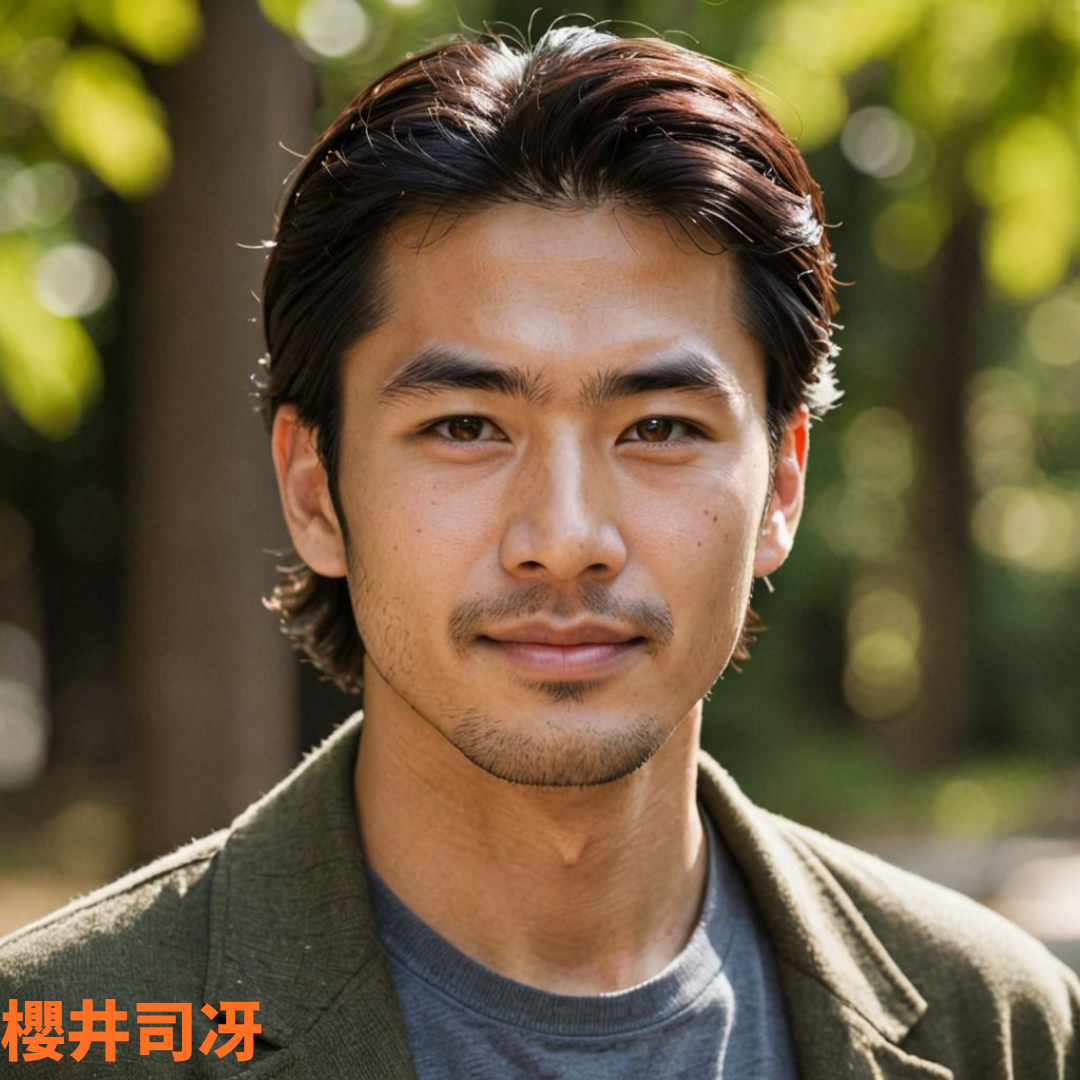
どんな生徒なのか理解を深めるためにも1度は行くといいと思います。
優しい雰囲気でかつ、頼りになると思われるような雰囲気が出せるといいですね。
学校に来る・来ないは本人の判断なので、行ってみてもいいなと思わせれるそんな訪問がいいですね。
学校の配布物を持っていくこともあるかと思いますが、本人に渡すかどうかは慎重に判断しましょう。
学級のお便りなどは持って行っても本人の心理的負担が増さないか検討してから持っていくか考えましょう。
4月、新学年スタートの初めの学級通信は持っていくと思うので気合い入れて作るといいですね。
凡事徹底4:言ってはいけない言葉は絶対言わない
生徒によっては、NGとなっている言葉があることがあります。
どんな生徒であっても、不登校を軽視した発言やその生徒を否定するような発言はしないようにしましょう。
より学校から足が遠のく可能性が高いです。
上2つのような不登校を軽視するような言葉や、不登校差別とった話はもちろんいけません。
しかし、中には「がんばろう」などの言葉もNGと感じる生徒がいます。
生徒とのかかわりの中でしか獲得できないものなので、生徒の引継ぎ資料に入れておくことがおすすめです。
保護者との話の中で、聞いてみるのもいいかもしれません。後から先生に言われて嫌だった言葉はあったか確認してもらうといいですね。
不登校傾向の児童・生徒への凡事徹底
不登校児童・生徒への凡事徹底ももちろん行っていきますが、不登校傾向のある生徒の場合は、学校に登校してくるので、登校時に注意が必要なことがあります。
基本的には以下の3つです。
いくつか具体例を交えて凡事徹底を解説していきます。
過去に不登校だった生徒
体調不良などからくる遅刻早退が多くなってくると不登校に戻る傾向にあるので、速めの対応が必要です。
小学生・中学生の場合は、「学校に来てくれてうれしい」「よく頑張ってるね」と肯定的な声掛けを行いましょう。
教室で座っているのがつかれるなどの症状がある場合、保健室1時間だけ休ませるなどの対応も必要になってきます。無理に頑張ると翌日休む可能性もあります。
また、不登校時代の学習の遅れが心配ですので、習熟度別の授業を行っている場合は教科担任に相談し、できそうな内容から少しずつ学習を積み重ねていくのが効果的だと思います。
いきなり難しいところから始まってしまうと学習に対する意欲まで低下してしまいます。
一度不登校になっているので、担任だけで問題解決に向かうのではなく、保健室や相談員と連携する必要があります。
クラスに苦手な生徒がいて登校しづらい
学校内に安心して過ごせる場所の確保が必要です。保健室や図書室、空き教室などを確保しておきます。
安心して話せる大人を1~2人用意できるといいです。担任でも養護教諭でも誰でもいいですが…。
また、苦手な度合いにもよりますが、座席や活動班を工夫する必要があります。座席の並びから不登校に発展する可能性もあります。
急いではいけませんが少しづつ関係改善に努めます。段階的に、少しづつです。
関係改善が難しい場合は、次年度以降クラス替え等で配慮の必要が出てきます。

発達特性が関係している生徒
発達特性が関係している生徒の場合は、音や人混みが苦手なことがあります。そのため、学習環境の工夫が必要になるケースもあります。
周囲の子たちと少し違うと感じた場合は、特別支援教育コーディネーターや専門の相談機関と連携して課題解決に向かいます。
私のクラスにいた生徒は感覚器官の検査から教室で対応するまでに、3か月かかりました。保護者に相談し、専門機関で検査して、結果を踏まえて特別支援教育コーディネーターと対応を考え、学年で意思疎通をしてから、教室で対応。
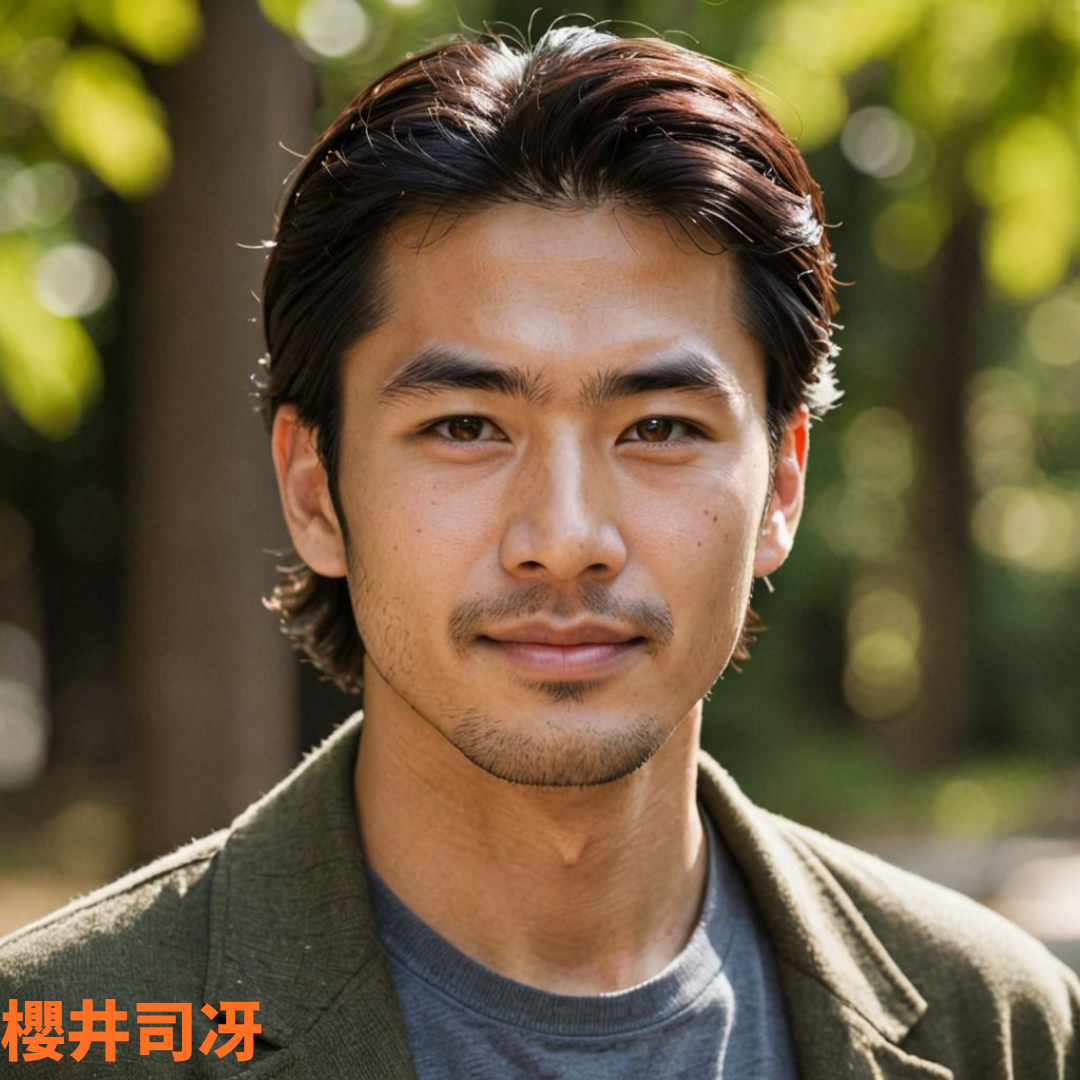
専門機関を利用すると本当に長い時間かかるので、思い立ったらすぐ学年主任や管理職に相談するのがいいと思います。
ネット依存等による昼夜逆転
学校では特に問題視していないこともあると思います。「朝が弱い子」の原因を深堀していくとここにたどり着くことがあります。
スマホを禁止にしてもストレスから別問題に発展しかねないので、依存となった背景に注目し解決していくのが良いです。
先生としても「ネットが良くない」と伝えるのではなく、「現実の友達や学校でも自分の居場所がある」と伝えていく方がいいです。
現実の行動を褒め、どんどん価値づけし、居場所を作ってあげましょう。
いじめやトラウマによる不登校傾向
実際に接してみるとなかなか話してくれない。俯き具合で「時間が過ぎるのをただ待っている」そんな印象でした。
学校=危険なところと感じていて、生徒も教員も信じられないという感情を持っている生徒が多いと思います。
別室登校や個別対応の検討が必要になります。安全な環境を用意するのが最優先です。
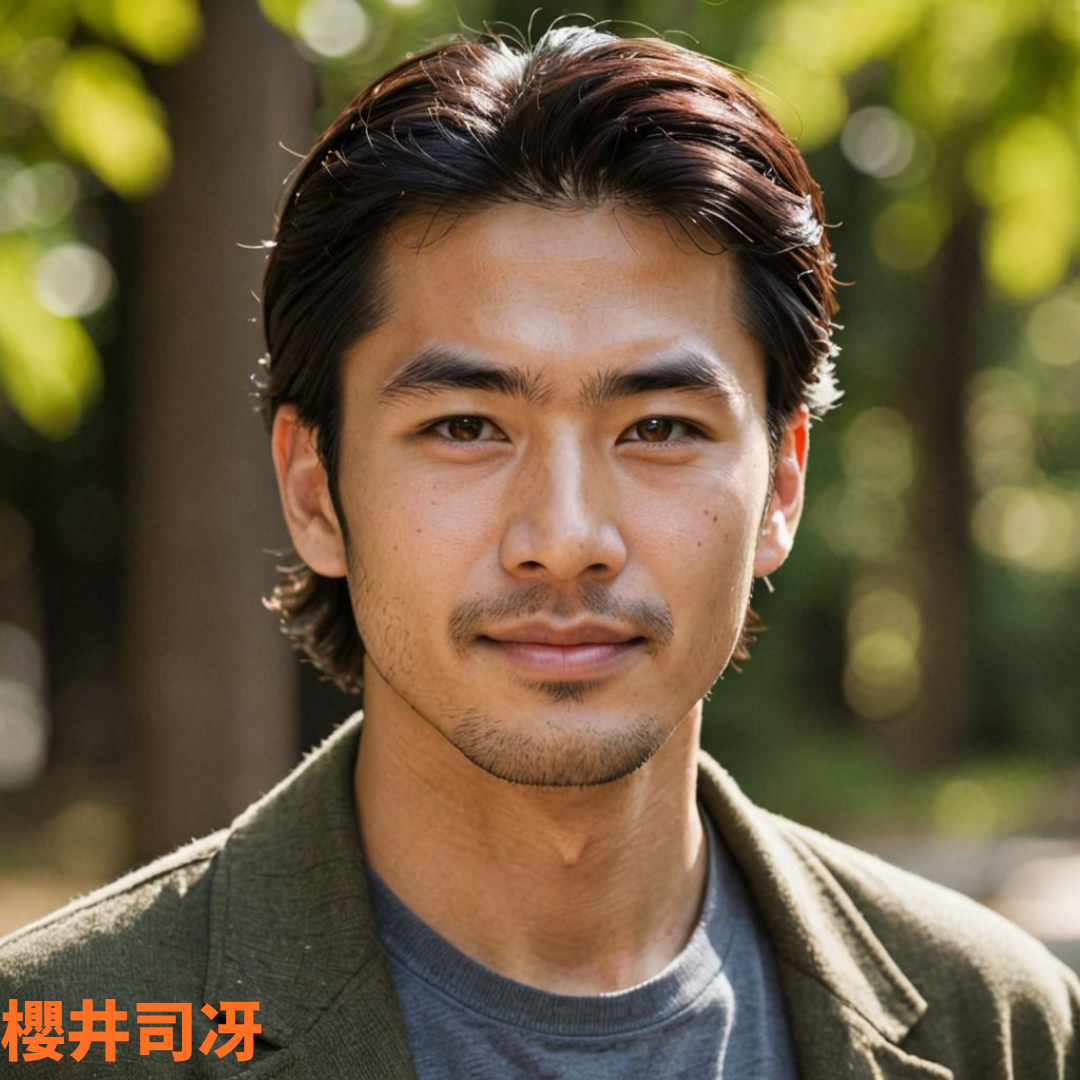
信頼関係の回復には時間がかかるので、安全な場所を作ってスモールステップで成長を促します。
週1回学校に登校するというところから徐々に投稿頻度や教室に入る頻度を増やしていくのがいいですね。カウンセラーや学校心理士などと連携する必要が出てきます。
そもそもいじめの加害者が登校していると登校したくないと感じると思うので、何らかの懲戒が必要だと思います。
生徒の懲戒については下記記事で解説しています。
さいごに
一口に不登校傾向と言っても様々な生徒がいます。
不登校となる前に、担任だけでなく部活動顧問、授業にでる先生含めみんなでその子を見ることが大切になります。
不登校に「これをすればよくなる」万能薬はありません。ただ、新学期が始まるときは不登校生徒への対応に特に力を入れていました。
やる気ある4月頑張りすぎないようにブレーキをかけつつ、適度に成長を促していきましょう。