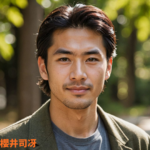【体罰禁止】先生は生徒にどこまでしても許される?正当防衛や懲戒を解説

- 生徒に対してどこまでの指導が許されているのか
- 教育困難校では、どうなっているのか
- 自身に危害が及ぶ場合はどうか
こんにちは、つかさの教室教室長のつかさです。
近年、小学校での暴力行為の増加がささやかれています。小学校で、増加すれば、中学高校と順に増加していく事が目に見えています。
この記事は教員のみなさん向けて、体罰禁止の事実や、自分なりの解釈を紹介します。
「この記事をよんだから、このように指導した」というのではなく、この記事を参考に生徒指導部会などでよく相談の上、各校の指導にあたってください。
体罰禁止に関する通知
平成25年、文部科学省による以下のような通知が出ました。この通知を参考にしつつ、独自の解釈も書いていきます。
この中に明記されていますが、体罰は学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはなりません。
絶対に殴ってはいけません。物も投げてはいけません。どんな場合であっても指導の一環で、生徒に身体的苦痛を与えてはいけないのです。
懲戒と体罰の区別
懲戒(ちょうかい)と呼ばれる行為と体罰は明確に区別されています。
懲戒は普段から行っている生徒指導上の行為になります。これからも必要に応じて行っていく必要があります。
懲戒と体罰について表にまとめました。
| 具体的な行為 | |
|---|---|
| 懲戒 | 学校教育法施行規則に定める退学、停学、訓告。 また、肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と考えられる以下の行為 ※注意、叱責、居残り、別室指導、 起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導 など |
| 体罰 | ・懲戒行為の内、内容が身体的性質のもの ※身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等) ※肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等) |
身体的苦痛を伴うと体罰になるというのが、ポイントです。通常の範囲内で指導する分には問題ないということ。
再確認ですが、殴る蹴るに該当する行為は、絶対にしてはいけません。
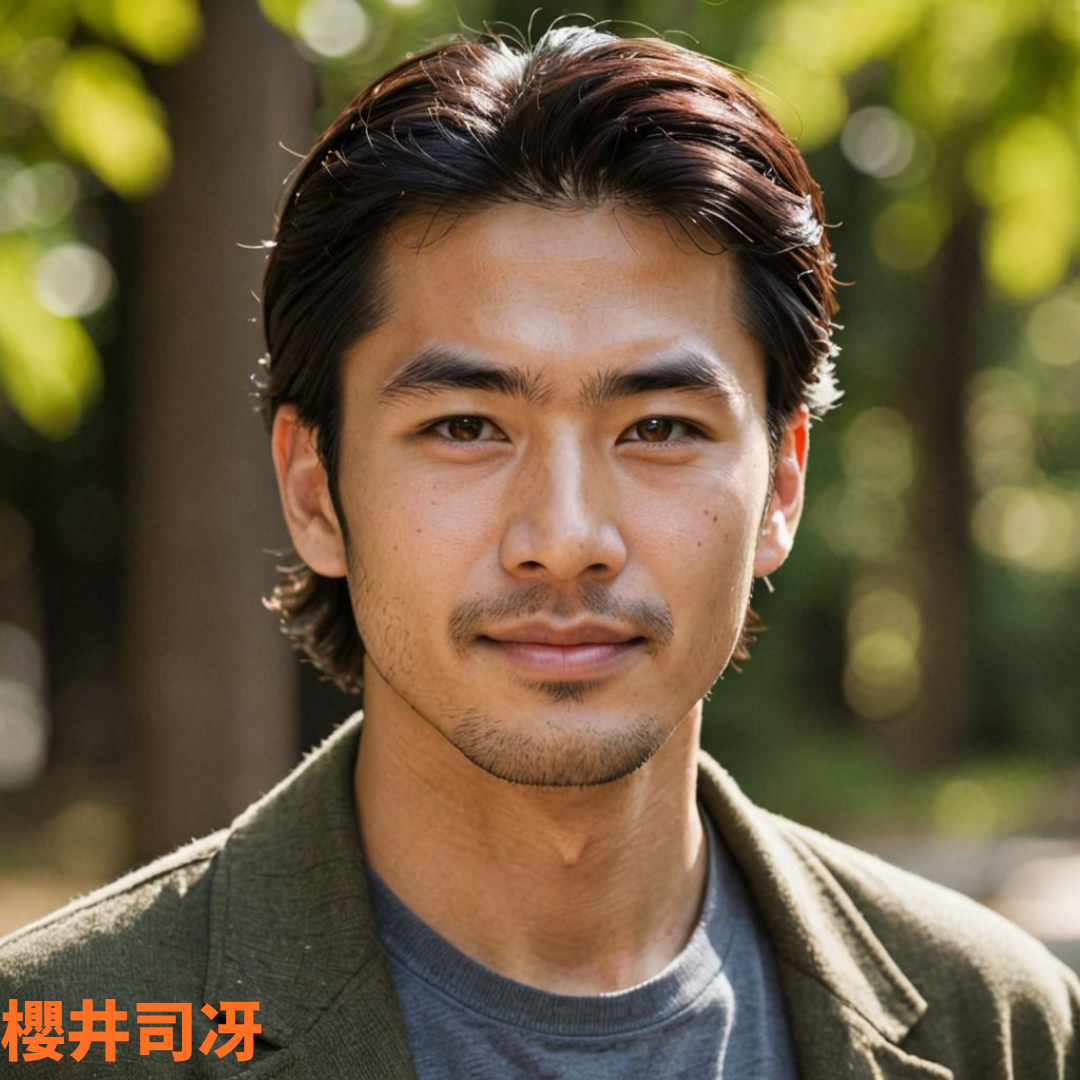
私は怒るときに腕組みするようにしてました。
間違って手でもカスったら、「殴られた」「たたかれた」となりますので注意・叱責する際は、距離を保ちましょう。
また、体罰になるかならないかの判断について以下のように書かれています。
当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
文部科学省ー体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)ー
個室でみっちり、というのは時代的にもよくありません。時間をかけず、グッと指導して終わり。それが理想です。
また、時間がかかる問題行為に対する指導には必ず教員2名以上で対応します。女子の指導の場合は、女性教員が1名はいた方が安心です。
正当防衛と正当行為
正当防衛と正当行為に関してもしっかりと明記されています。
(1)児童生徒の暴力行為等に対しては、毅然とした姿勢で教職員一体となって対応し、児童生徒が安心して学べる環境を確保することが必要である。
(2)児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛又は正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
文部科学省ー体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)ー
言葉を簡単に書き換えます。
- (1)児童生徒の暴力行為は、他の大多数の児童生徒を守るために厳しく指導にあたる必要がある。
- (2)児童生徒に攻撃された場合は自己防衛をする。自己防衛の一環で、児童生徒に攻撃しても体罰にならない。
- (2)児童生徒が、他の児童生徒に危害を加えそうなとき、危険回避のために行う行為は体罰にならない。
生徒を守るため、自分を守るために行う行為は体罰に該当しません。
カッターを振り回している生徒がいたときに、体罰にならないかどうか考えていたら対応が遅れますよね。全力で、刺股でも盾でも良いので使って押さえる必要があります。
それがその児童生徒の為にもなります。他の生徒に危害を加える前に止めましょう。
部活動も例外なく体罰禁止
特定の生徒に、執拗に過度な肉体的疲労を伴う練習を継続していた場合、体罰行為に該当する可能性があります。
健康的で、心身の成長にとって必要と判断されるレベルの負荷は必要ですが、やり過ぎには注意が必要です。
教育困難校・いじめの場合
そもそも教育困難校=暴力行為が横行しているというわけではないので、暴力的な行為を行う人間が複数存在している学年について、紹介します。
いじめなどの行為も同様の対応ができるといいのですが…。
暴力行為を繰り返す場合
生徒指導担当に報告して対応に当ります。保護者や警察、教育委員会などと連携して対応にするのがいいです。
何かあってからでは遅いので、警察にも相談しておけば良いです(もちろん管理職の判断で、です)。
他のクラスメイトが不登校や登校渋りが出てくる前に、強い対応が必要になります。
公立学校の場合、退学等はできないため、校長命令による停学、教育委員会による出席停止命令を行うことはできます。
停学も出席停止も本人への懲戒という意味ではなく、学校の授業を通常通り行えるようにするための手段です。他の生徒の学業継続を優先する結果です。
停学等も視野に入れて進めていく必要があります。
暴力行為ではないが危険行為を繰り返す場合
これも管理職や生徒指導担当に報告します。警察などにも相談しておくと良いです。
「体罰ができない」ということを、暴力的な児童生徒も理解している事が多いです。
体罰ができないので、こちらが正当防衛、正当行為を行えるかギリギリのラインの行為を行うことが多くなります。
自身に危害が及ぶ前に、対応する必要があります。
当該児童生徒が行っている行為は誰に対して行っているのか、いつ行っているのか等を複数教員で観察・監視し、行わないようにさせていく必要があります。
無理なら無理で、停学・出席停止命令です。他の生徒の安全を最優先にすべきです。
いじめの場合
いじめの場合は、被害児童・生徒がいます。
学校は安全な学習空間を提供する必要があるので、いじめ行為=懲戒の対象となります。
加害者側が別室登校になれば、一時的ではありますが被害生徒は安心して教室に入ることができます。
ただ、加害生徒が教室に戻る際に反省していない場合、行為の繰り返し・行為のエスカレートが考えられます。毅然とした対応が求められます。
管理職が動かない場合
よくあります。「そういう生徒もいるから大丈夫。根気強く指導していれば変わる。」と言われ相手にされない事もあります。
現代の学校は、それでは難しいです。関係機関や家族と連携する必要があります。
管理職を説得し、生徒指導の基準を明確に制定しておくことにほかないです。
以下、例ですので、このような資料を生徒指導部会などで作成して起案してください。すでに、生徒指導の基準、段階等が明確に存在している場合はその基準を基に指導に当りましょう。
| 行為の程度 | 学校の対応 | 対応する教員 | 保護者連絡 | 関係機関への連絡 |
|---|---|---|---|---|
| ステージ1 ・他の大多数の生徒に影響のない問題行動 | ・当該生徒個別指導 | ・担任 ・学年主任 | ・即日連絡 | ・なし |
| ステージ2 ・ステージ1を繰り返す場合 ・他の大多数の生徒に影響がある行為 | ・当該生徒個別指導 ・危険物預かり ・3日間別室登校 | ・担任 ・学年主任 ・生徒指導主任 | ・即連絡 ・担任、学年主任、保護者立ち会いで面談(放課後) | ・警察に相談 ・学校SCを利用 |
| ステージ3 ・ステージ2お繰り返す場合 ・学校全体を危険にする行為 | ・5日間、花壇の清掃、窓磨き等を行う ・別室に登校する ・場合によって停学処分 | ・学年主任 ・生徒指導主任 ・管理職 | ・即連絡 ・学年主任、生徒指導担当、保護者立ち会いで面談(放課後) | ・警察に相談 ・学校SCを利用 |
| ステージ4 ・ステージ3を繰り返す場合 | ・停学処分 ・教育委員会へ連絡 | ・生徒指導主任 ・管理職 | ・生徒指導担当、管理職、保護者立ち会いで面談(放課後) ・出席停止命令 | ・警察に相談 ・教育委員会に連絡 |
あくまで、この表は例ですので、中身は学校の実態に合わせて変えてください。懲戒の処分が重いと感じる場合は、別室登校3日などでもよいです。
ステージ分けを行いステージ2を越えたら警察に相談しよう、教育委員会に相談しようと決めておく。
担当者についても、ステージが上がると管理職が入ったりするように決めておきます。同じ行為を行っていて、担任から指導され続けているより改善の可能性があります。
他の生徒の日常が保たれるように、判断基準と懲戒の処分を明確に資料にまとめます。
懲戒の種類等に関しては、事前に保護者に周知しておく必要があります。
まとめ
場合によっては体罰もやむを得ない、という時代は終わりました。
正当防衛の範囲内で、行う行為は問題ないだけで、基本的に児童生徒に対して、手が当るだけでも体罰になる可能性もあります。当たり前ですが、過剰防衛はしてはいけません。
二人だけの密室での指導は行わないでください。密室より廊下の方が良いです。他の教室で指導を行う場合は、生徒1名に対して教員2名を配置し、連携しながら行いましょう。
教員2名配置できないくらい重大な事案の指導の場合は、一度児童生徒のみを別室に待機させ、準備が整ってから指導に当りましょう。
セクハラの基準とも似ていますので、生徒指導を行う際も密室で二人きりは、避けましょう。
アンガーマネジメントの観点からも、1人での指導よりも冷静に指導に当ることができます。