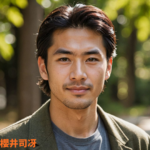【不登校未然防止】不登校の始まりは1月、4月、5月、9月。保護者ができるひきこもり予防策とは

つかさの教室 教室長のつかさです。不登校生徒と関わってきた中から見えてきたこと、学んだことを記事にまとめています。
近年になってなぜ、不登校が増えたのか。不登校になりやすい時期は調査で、1月、4月、5月、9月と分かっているのに減らないのです。
原因はお家にあることも多いので、この記事では対策についてまとめておきます。
「不登校傾向」の生徒とは
2018年10月に中学生年齢の12歳~15歳合計6,500人を対象にインターネットで行われたアンケートでは、「年間30日以上欠席の不登校である中学生」は約10万人、「不登校傾向にあると思われる中学生」は10.2%の約33万人に上ることがわかりました。
不登校である中学生約10万人は文部科学省が毎年調査していますが、「不登校傾向にあると思われる中学生」の数はその3倍です。
そもそも不登校の定義は数字です。
・何らかの、心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。
ー文部科学省ー
おかしな話でもあるのですが、数字で線引きしないと正確に集計できないので、30日以上休んでいれば不登校です。
では、不登校傾向のある生徒とはなんなのか。
これが、こどものSOS信号なのです。
保護者はSOSを受け取る必要がある
問題は、この実態を「保護者の皆さんが確認できているか」です。以下のような場合は要注意なんです。
・学校に行っていると本人は言っているが、登校していない(学校外にいる)
・元気に朝出て行くが、教室に入れていない
・家では「楽しい」アンケートでは「行きたくない」
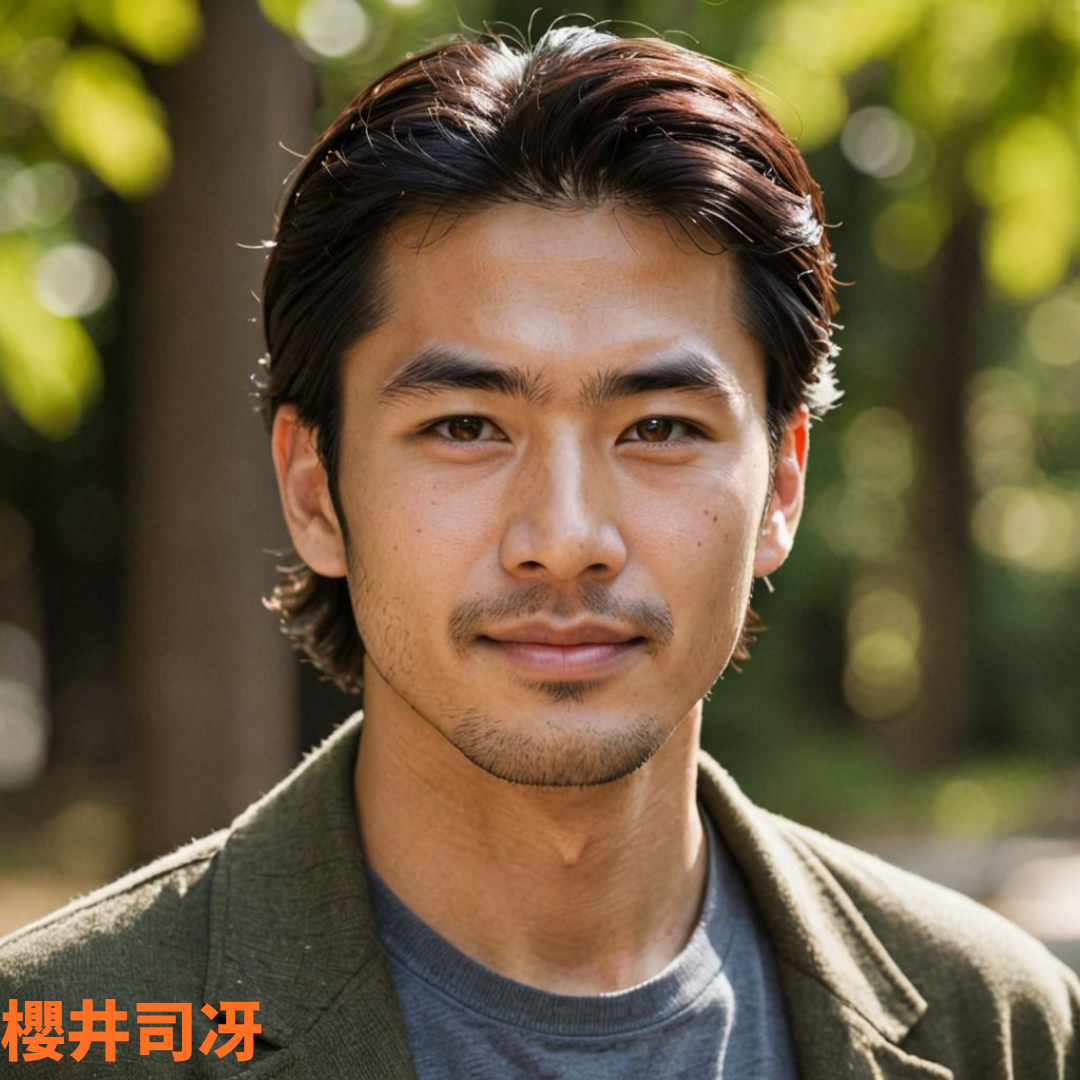
私の勤務していた学校では、遅刻の時点で保護者即連絡です。(事前連絡なし遅刻の場合)
生徒の身にもしもの事があってはいけません。
別室登校も初日の時点で放課後(仕事終わりの時間)に即連絡、場合よっては3者面談や2者面談を実施してました。
アンケートは学期毎に行われるので、すぐに生徒と面談を実施します。何かありそうなら、保護者に協力を仰ぎ対応してもらう。
しかし、令和の学校は多忙なので、連絡の遅い学校もあるのは事実です。
対応が遅ければ遅いほど、不登校につながる可能性は高くなります。なので、家でもしっかり見守るひつようがあります。
- 不登校の原因
-
・無気力
・非行や遊び
・学業不振
・甘えたがり・精神が未熟
・家庭環境(金銭的問題、介護、家庭内不和など)
・発達障害
・神経症別記事で解説予定です。
不登校の始まり

不登校(登校渋り)のきっかけとして多いのが4月、5月、9月、1月です。
「不登校のきっかけ」を言い換えるなら「欠席が多い時期」です。
なぜ、この時期に欠席が多くなるのかを知っておくことで、不登校傾向のあるお子さんをサポートすることができます。
9月と1月は同じ理由
学校の「夏休み明け」「冬休み明け」となるこの時期は、問題が起こりやすいです。
原因となる人間関係・無気力・体調不良が非常に起こりやすい時期なのです。
一人一人不登校となる要因は違えど、この時期に集中しているので対策が必要です
4月に多い理由
環境が大きく変わり、「頑張るぞ」と「不安だ」という感情が交じった春。幸い天気は三寒四温で徐々に暖まるものの、大きな不安を抱える生徒にとっては曇天の日はしんどいでしょう。
変化の大きな4月ストレスも並大抵ではありません。
新しい担任と合わない場合も多いです。
まあ、中学校・高校の場合は担任の授業も少ないので、小学生と比較してそこまで気にする必要はありません。
でも、気にする子は気にしますし、担任が嫌だから不登校になる事例も存在します。
5月に多い理由
「五月病」正式な病名ではないですが、近年ニュースなどでも取り上げられることの増えた症状が子どもたちに如実に表れます。早い子は4月中旬から起こります。
児童生徒の場合は原因も多様です。
4月の疲れが溜まった状態での連休で、一気に無気力になることも多くあり、よく観察する必要があります。
また、小学校の場合は運動会も5月にあることが多く、運動会終わりから学校に行けなくなるケースもあります。
不登校・登校渋りの初期対応
子どもの問題は、早期発見・早期解決です。傾向があることを理解した上で接していきましょう。
まず、親の心構えとしては「心配しすぎないこと」を意識してください。
心配しすぎるあまり、強い言葉をかけた・聞きすぎて拒絶されたという話もあります。ほどよく心配していく必要があります。
子どもの出すSOSを見逃さない
特に、4月、5月、9月、1月は注意して観察、コミュニケーションをとるようにしましょう。
良いことも見えてくるはずです、朝早く起きるようになったな。いつもより5分早く家を出て行くな。些細な変化に気付きましょう。
伸ばしたいところは褒めて、頑張りすぎでは?と思うところは心配してあげましょう。
子どもからSOSが出るときにはしっかり対応しましょう
体調不良の場合は、休ませるだけでなくしっかり病院に行き原因を特定する。腹痛なのにゲームして過ごすというのはダメです。
「なぜ行きたくないのか」「なぜ手を洗うことに執着しているのか」「なぜ兄弟にあたるのか」原因があります。探りましょう。
行事で何かあった可能性もあります。容姿をいじられた可能性もあります。いじめられているケースもあります。
よく話を聞いてあげる
一緒に居る時間を確保しておきましょう。
朝から晩まで自分の部屋ではなく、起きたらリビングで過ごす。帰ってきたらお風呂終わるまではリビングで過ごすなど習慣化しておくと良いのですが、思春期に入るとなかなか難しいです。
夕食のタイミングなどで、学校の話を聞くなどしても良いかもしれません。
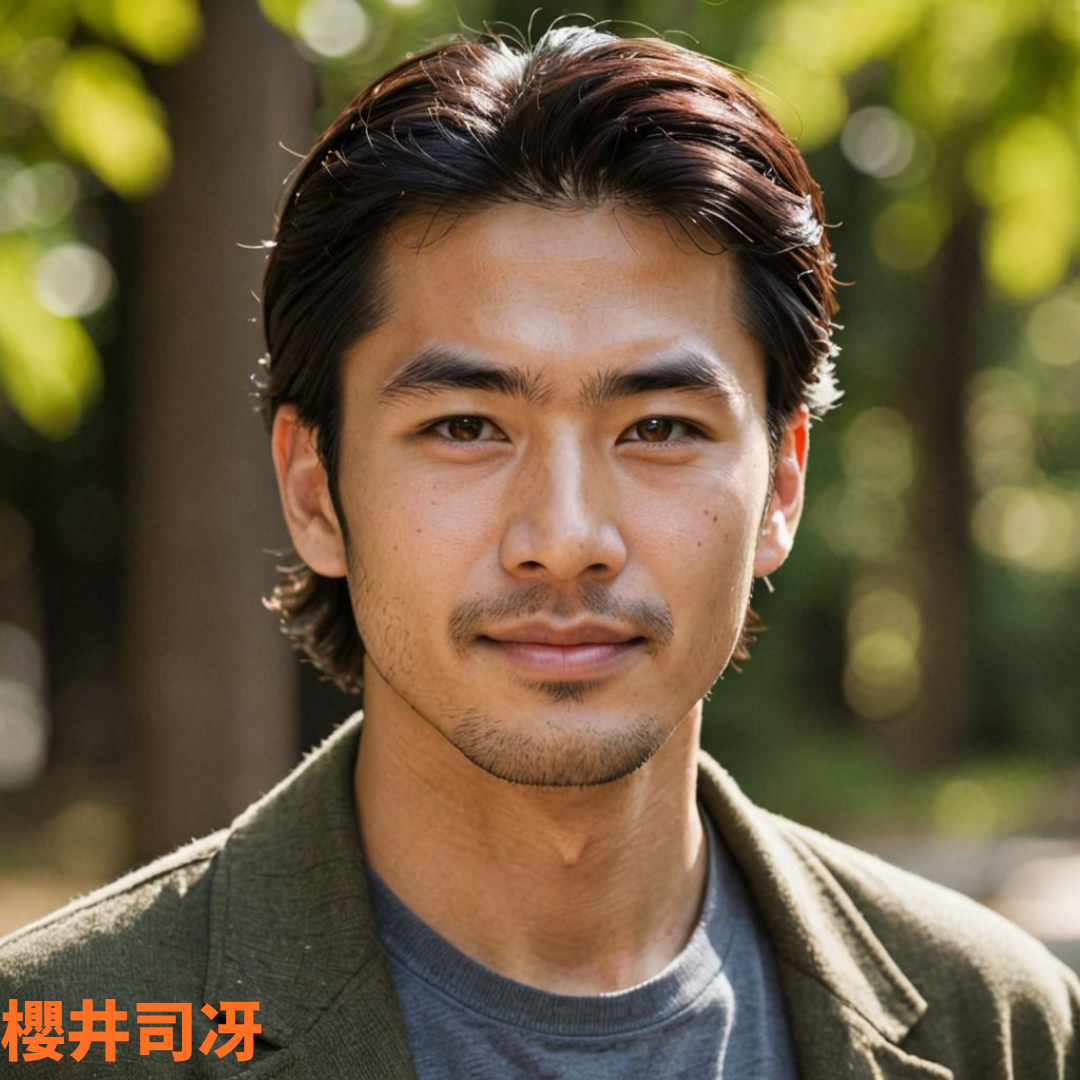
聞こうとするあまり、必死になってはいけません。自分で理由が分かっていない場合も多いです。
もし、それとなく聞いて、拒絶されるなどした場合は、一旦聞くのをやめましょう。
心配して寄り添ってあげましょう。話せる悩みなら解決してあげましょう。
休ませることも大事
連休明けの初日、2日目と登校はしてるものの表情が暗かったり、落ち込んでいる様子がある場合は、計画的に休ませることも必要になります。
表情が暗いのに学校に通わせ続けることで、ストレスとなり体調を崩す可能性もあります。
学校と連携して対応にあたる
朝に突然「学校に行きたくない。学校には体調不良と伝えて」のように、理由を言いたがらない生徒も多いです。
学校に欠席連絡する際にそれとなく、学校の先生にきいてみるのもいいとおもいます。
連絡した際に担任と話せなかった場合は、担任と話したい旨を伝えておきましょう。
登校渋りのスタートは学校側も敏感です。
友達と喧嘩をした、学校の物を壊した、クラスメイトがうざい、仲間はずれにされた、学校での強い指導があった。先生側でも心当たりがあるかも知れません。
最後に
大人にとっては些細な出来事に感じることでも、子どもにとってはとても大きな出来事です。
話を聞ける人間関係の構築が必要不可欠ですし、常日頃からアンテナを貼っておく必要があります。
不登校傾向かな?と思ったときから動けているか、年間30日休んでから対応するのかでは、効果が全然違います。
思い立ったらすぐ行動していきましょう!
不登校になったときの対処法については別記事でまとめる予定です。お待ちください。